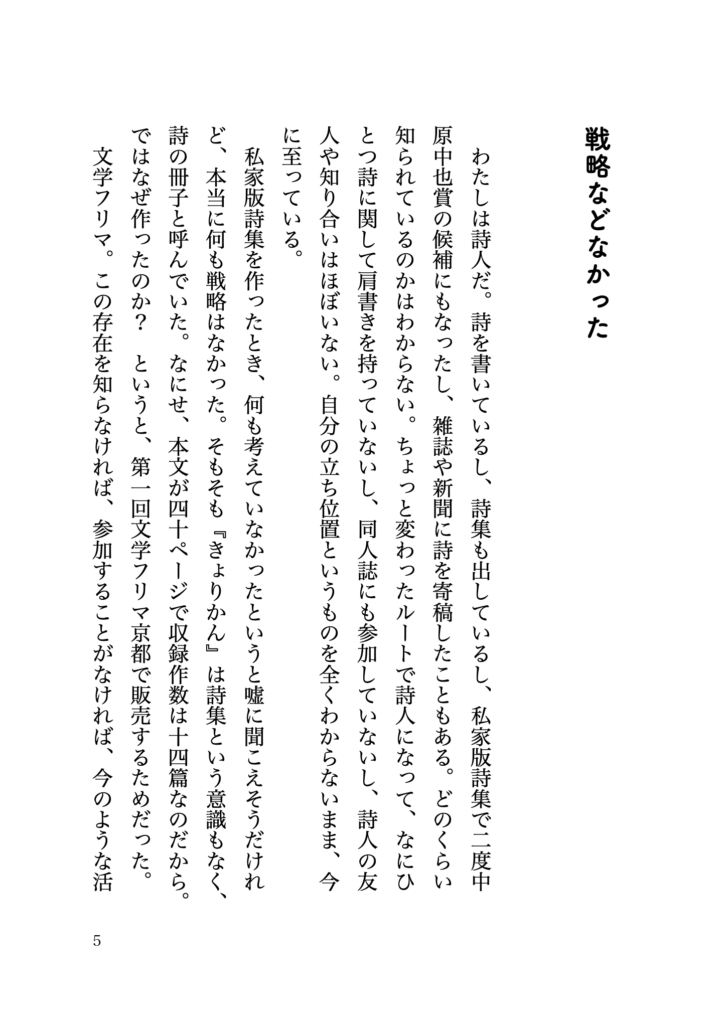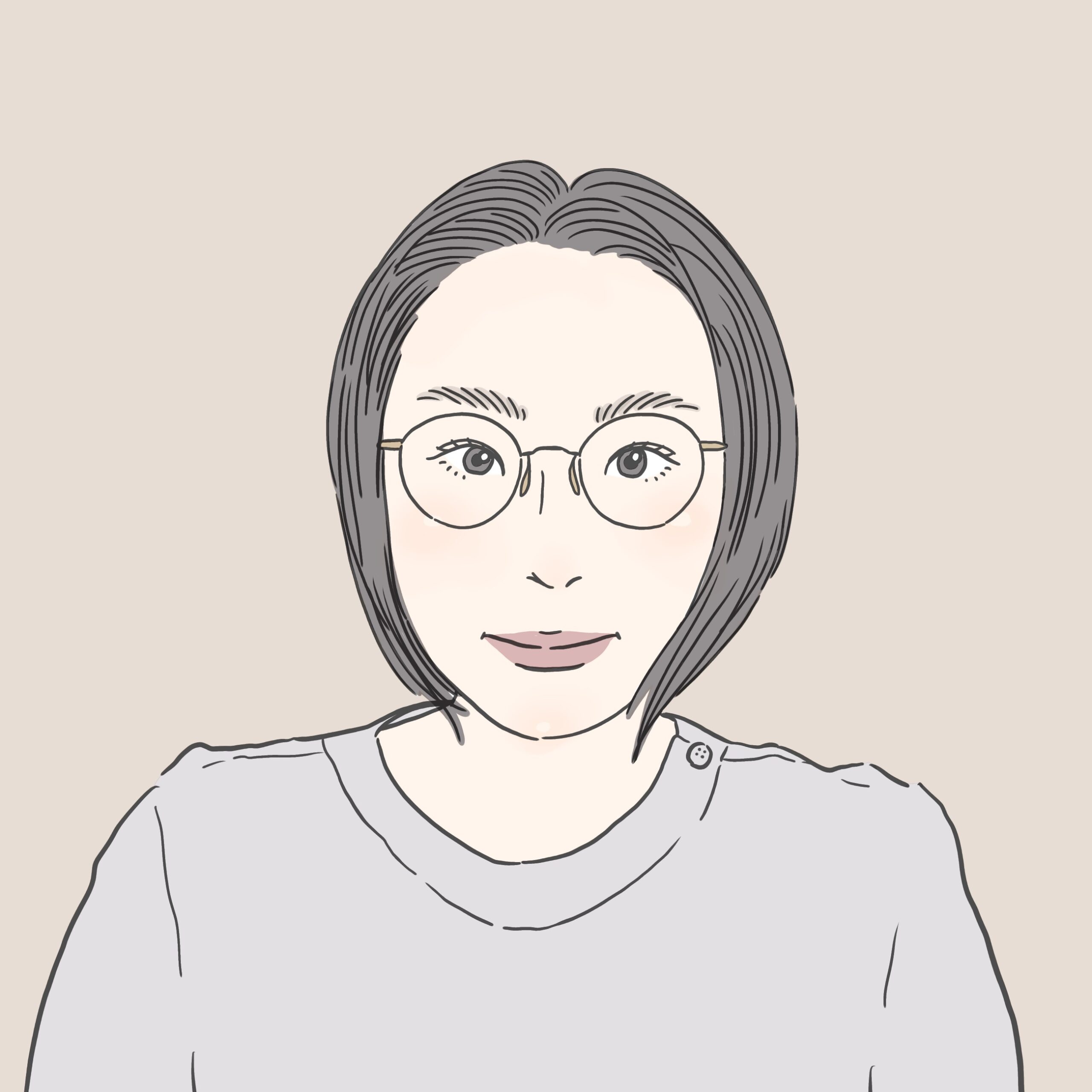わたしは詩人だ。詩を書いているし、詩集も出しているし、私家版詩集で二度中原中也賞の候補にもなったし、雑誌や新聞に詩を寄稿したこともある。どのくらい知られているのかはわからない。ちょっと変わったルートで詩人になって、なにひとつ詩に関して肩書きを持っていないし、同人誌にも参加していないし、詩人の友人や知り合いはほぼいない。自分の立ち位置というものを全くわからないまま、今に至っている。
私家版詩集を作ったとき、何も考えていなかったというと嘘に聞こえそうだけれど、本当に何も戦略はなかった。そもそも『きょりかん』は詩集という意識もなく、詩の冊子と呼んでいた。なにせ、本文が四十ページで収録作数は十四篇なのだから。ではなぜ作ったのか? というと、第一回文学フリマ京都で販売するためだった。
文学フリマ。この存在を知らなければ、参加することがなければ、今のような活動はしていなかった。明確なものは忘れてしまったけれど、ネットで「文学フリマ」なる文学作品の展示即売会の存在を知り、楽しそうだなぁと思って公式サイトを見ていたら、大阪でも開催されているではないか。大学時代の文芸部仲間に声をかけて、二〇一五年九月の第三回文学フリマ大阪に遊びに行った。この頃は天満橋のOMMビルではなくて、地下鉄御堂筋線の終点なかもず駅近くの堺市産業振興センターが会場だった。それまで、本といえば商業出版で、何とかして賞を取るなりなんなりして出版社から出すものだと思っていたから、出店者が思い思いに自分の作品を本にしている姿やその熱気に驚いた。いくつか本を買って、今度は自分が出店側に回りたいと思って帰った。ちょうど、詩を本格的に書き始めた頃だから、二〇一五年に書いた詩をまとめたら一冊作れそうだった。
そうして作った冊子が『湖面』で三十部作って、二〇一六年九月の第四回文学フリマ大阪に出店した。思えば今よりのんびりした雰囲気で、店番をしながら読書をし、来てくださった方とおしゃべりしていた。そこまで売れないだろうと思っていたけれど、蓋を開けてみたら半分ちょっと売れた。「お金を払って買ってでも、わたしの詩を読んでくださる方が存在する」ことを実感した。すごく嬉しかった。対価を払うということは価値を認めているということだから。この経験がわたしの活動の原点にある。気をよくしたわたしは、「自分の詩はどこまで通用するのだろう」と思って詩誌への投稿を始め、二〇一七年一月の第一回文学フリマ京都にも申し込んだ。
第一回文学フリマ京都に向けて『湖面』を増刷するという発想にはならず、新しいものを作ろうと思い立ってできたのが、『きょりかん』だ。半年分の詩をまとめて、少し多めに五十部作った。この時の記憶があまり残っていないのだけれど、終盤も終盤、もう片付けを始めていた頃に駆け込みで買いに来てくださった方がいたのを覚えている。こういう、わたしは覚えていてもご本人は忘れているだろうことの積み重ねで、活動を続けている気がする。『きょりかん』は多めに作ったから、第五回文学フリマ大阪でも販売したし、委託販売のお店「架空ストア」でも販売してもらった。二〇一七年の秋、まだ手元にある『きょりかん』を眺めてふと、表紙と奥付けがあるから中原中也賞に応募できるのでは? とひらめいた。それで応募して、受領書のハガキが届いて満足していた。
満足していてすっかり忘れていたら、第二十三回中原中也賞の最終候補になっていた。もう手元にほとんどなかったので、とにかく大慌てで『きょりかん』新装版を作り、詩誌への投稿は終えて投稿時代の詩をまとめた『ひかりがやわい』を作った。出版社から出すにはお金がないし、そこまでの知名度や実力があるとも思わなかった。ただ、制作部数は増やしたし、客として行っていた本屋さんに声をかけてお店に置いてもらうようになった。
三冊目の『声を差し出す』は二〇一九年五月から七月くらいまで作業をした後止まっていたのだけれど、十月あたりにどうしても二〇一九年のうちに、それも中也賞の締切に間に合ううちに作りたいと思って大急ぎで作った。中也賞に出す、そのあとはまた考えるみたいな感じだったので、戦略と呼べるほどのものはない。応募してドキドキしていたら、無事候補になったので一安心だった。ずっとビギナーズラックだったらどうしよう、という気持ちがどこかに引っかかっていた。
そのあと、コロナ禍に入ってしまってなかなか私家版詩集を販売する機会がなく、また、『声を差し出す』で私家版詩集としてやれることはやった気がして、一度出版社から出してみよう、と思ったのが『あかるい身体で』だ。
戦略的に詩集を作って活動してきたというよりは、行き当たりばったり、その時にやりたいことをやりたいようにやってきた。それでいて、一定の評価をいただいているので、ありがたいことだなぁと思っている。